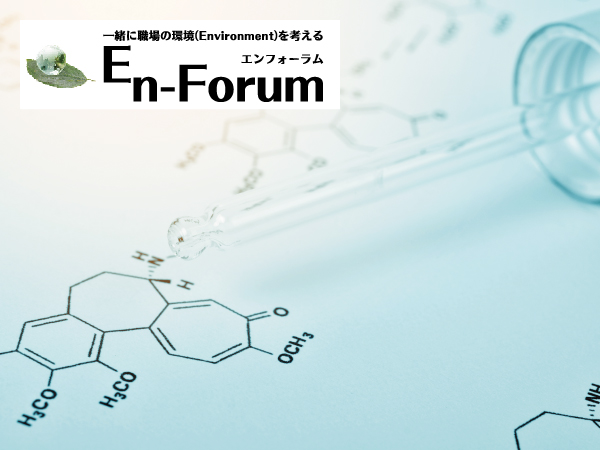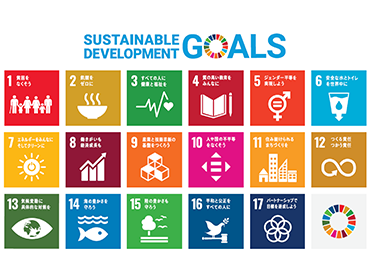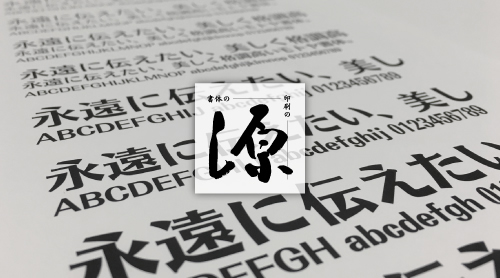~シリーズ:人材を守る~
災害対策を考える:水害対策
前回は自然災害等の緊急事態に被害を最小限にして、事業を早期に復旧するための計画「BCP」と、その中小企業版の「事業継続力強化計画」を取り上げました。今回は実際の自然災害から、水害対策を考えます。
日本で起こる自然災害で最も発生件数が多いのは台風で、全体の57.1%も占めます。2位が地震で3位が洪水と続きます。※中小企業庁より この台風は風の被害が大きいですが、大雨や洪水も伴って被害が拡大するため、自然災害の発生件数で半数強を占める台風と、3位が洪水であることを考えると、日本では水害が最も遭遇しやすい自然災害と言えるかもしれません。
そして、その水害が起こりやすい時期をみると、5~7月は梅雨前線による大雨、7~9月は上陸件数の多い台風、9~10月は降水量が増加する秋雨前線があり、日本では5月中旬~10月中旬までの約5ヶ月間も水害のリスクが高い状態が続きます。
また、近年の気象情報でよく耳にする「局地的大雨(ゲリラ豪雨)」と「線状降水帯」ですが、前者は短時間で局地的に降り、後者は発生した積乱雲が次々と線状に伸びていって、数時間かけて広範囲に降り続けます。どちらも正確な予測が困難で、近年の集中豪雨による河川の氾濫や水害の増加に繋がっています。これらは、前線の停滞や山岳地形の上昇気流で発生しやすいですが、温暖化や都心部の「ヒートアイランド現象」もその一因と言われています。
それは、ヒートアイランド現象がアスファルトの照り返しや建物の蓄積熱、空調の室外機から出る排熱が集まり、一帯の温度が上がる⇒上昇気流の発生⇒大雨を降らす積乱雲の発達を起こしやすくなり、予測ができない突然の集中豪雨へと繋がります。
では、これら集中豪雨への水害対策としては、土のうを積み上げて建物への水の侵入を防ぐ方法がありますが、土のうは1袋で約20kgもあり、水害対策に必要とされる高さ45cmまで積み上げるとなると2~3袋分の高さが必要で、わずか1mの幅に土のうを積み上げるだけで、大人2人で1時間ぐらいの重量作業となります。袋や土砂の準備まで考えると、急ぎで必要な分を用意するのは不可能なため、予測が難しい集中豪雨には対応ができません。
そこで、土のうに代わる水害対策『簡易設置型プラスチック止水板:ボックスウォール』をご紹介します。これは自立するL字型のプラスチック板で、高さ:約50cm×横:約1m/枚あり、土のうで約15袋分をほんの数秒で設置できます。重さは6.2kg/枚で簡単に持ち運べて、重ねて収納すると省スペースです。水圧で倒れず止めた水の重みでロックされる構造で、テスト環境では風速21m/Sにも耐えられる強靭さがあります。水平な地面に置いて繋げるだけで、誰でも簡単に設置が可能です。
集中豪雨などの水害は、ある日突然やって来ます。事前に地域のハザードマップをよくご確認いただき、浸水で大切な設備や資産を失う前に、手軽で効果の高い水害対策をご検討ください。
 ※ハザードマップポータルサイト
※ハザードマップポータルサイト